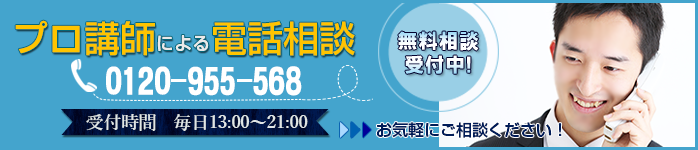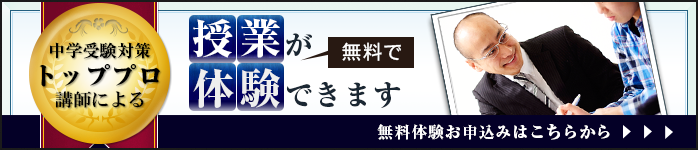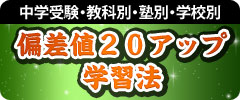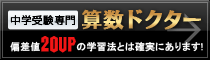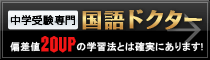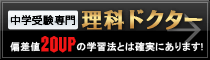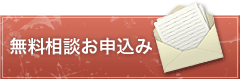社会の合否を分けた一題
慶應普通部入試対策・社会の合否を分けた一題(2020年度)
難易度分類
| 1) | 1.A 2.A 3.A 4.A |
|---|---|
| 2) | 1.A 2.A 3.A 4A 5.A |
| 3) | 1.A 2.A 3.B 4.B 5.B 6.A 7.B 8.C |
| 4) | 1.B 2.B 3.B 4.A 5.A 6.A 7.A 8.B |
| 5) | 1.B 2.A 3.A 4.B |
| 6) | 1.A 2.A 3.A |
A…慶應義塾普通部合格を目指すなら、確実に得点したい問題
B…知識、解法次第で、得点に大きく差がつく問題
C…難易度、処理量から判断して、部分を拾えればよしとする問題
出題総評
問題数ならびに問題の難易度は例年通りといえます。慶應義塾普通部の入試問題は、正確な知識がなければ正解を得られない点が特徴といえます。間違えている肢を、自信をもって切り落とせる、あるいは、正確な用語を空欄に入れられる『基本的知識の養成』が、合格への近道です。
問題別寸評
(地理)
地形図の問題です。一見すると、あれ?と思ってしまうような問題ですが、落ち着いて理論的に考えてみましょう。
1.
川の流れる方向を考える問題です。
当然に、水は高いところから低いところへ流れます。では、この地図では上(北)と下(南)ではどちらのほうが高いのでしょうか。等高線を見ると、左上(北西)から右下(南東)に向かって低くなっています。したがって、「河川はどの方向へ流れているか」ですから、南東が正解です。
2.
この地図の範囲で、土砂災害や水害がおこりそうな場所に関する問題です。
まず土石流とは、山に大雨が降った場合、谷や川に雨水が集中し、水や砂、石が一気にふもとに駆け下りるように流れてきて、家屋や人に甚大な被害を与える災害です。したがって、谷の出口が危険な地域となります。答えの一つ目は、「い」です。なお、地形図の問題で谷と尾根を見分ける問題が出されることがあります。谷は、等高線の凹凸が頂上に対してへこんでいるように見える地域です。本問では、まさに「い」の地域が谷です。尾根はこれの反対に、頂上に対してでっぱっている地域が尾根です。もう一つ、氾濫が起きそうな場所は、比較的大きな河川の近くです。河川の水が堤防を越えたり、堤防が決壊した際に、河川付近一帯が水浸しになることをいいます。したがって、「あ」です。
3.
等高線に関する問題です。
まず、等高線の間隔が20mごとに引かれていることを確認します。すると、A山の山頂は、630mと判断できます。他方でB地点は、すぐ北の等高線が500mと考えられますので、そこから等高線1本分低くなりますから480mとなります。630m-480mで、高さの差はおよそ150mとなります。
4.
本問は、可能性がある選択肢をすべて選ぶ問題であることがポイントです。一つ一つ欠けている部分にあてはめながら、可否を検討していきましょう。アは、欠けているほうに500mの等高線であろうものが書かれているだけですから、そのまま当てはまることがわかります。イは、500mの等高線が山道の両サイドに伸びていき、左下に向かって谷になるとみれば下っていくといえます。ウは、500mの等高線が一度閉じられて、左下でもう一度500mの等高線が復活します。したがって、左下に向かって登っていくような山道となってしまうため、条件に当てはまりません。エは、500mの等高線が、左と下の枠外すぐで閉じられているという可能性があります。したがって、このまま下っていく山道である可能性があります。以上から、ウ以外は欠けている部分に当てはまる可能性があるといえます。
歴史上の遺跡に関する幅広い知識を求められる問題です。
あ.が竪穴住居。い.が寺院。う.が一里塚。え.が御台場。お.が古墳。か.が貝塚についての記述と考えられます。
1.
2000年以上という長きにわたって遺跡が「つくられていた」期間についての問題です。存在していたという意味ではないところに注意が必要です。あくまでも、つくられていた期間です。まず、竪穴住居は、縄文時代から地方によっては江戸時代まで。その多くも平安時代までは作られていました。そして、貝塚です。縄文時代のゴミ捨て場などともいわれますが、縄文時代が約10000年つづいたことからすれば、2000年以上という条件に合致します。
2.
え.は御台場(お台場)です。現在もレインボーブリッジわきに当時の島と砲台跡が残っております。これは、幕末にペリーが来航したことをきっかけに、建設されたものです。ペリーがはじめて来航し、1年後の再来航を約束して帰国したあと、次回に来たときは追い払うつもりで急いで幕府が建設したのです。
3.
お.が古墳、か.が貝塚です。古墳から出土するものとしては、「はにわ・銅鏡」などが見られます。貝塚からは、「土器・動物の骨」などが見られます。木簡は、いまの手紙や伝票と同じ役割をしていたもので、とくに、律令制における「調」を都に運ぶ際、伝票として使われていたものがあちらこちらから出土しています。
4.
い.は、寺院に関する記述と思われます。寺院の図は、エです。中心に本堂があり、これを取り囲むように廊下が建造されていたことが見て取れます。また、右側中ほどに、塔らしき黒い点が見られます。お.は、古墳に関する記述と思われます。前方後円墳が描かれているイが正解です。
5.
竪穴住居を真上から見た図を描く問題です。
屋根の支柱は4本という条件ですので、下のように描いてみました。
(地理)
穀物の生産に関して幅広く問う問題構成となっています。
1.
正しくないと思われる選択肢を洗い出してみたいと思います。まずイですが、米の価格が「下がり続けている」と記されていますが、例えば、2003年は大幅な米価の上昇が見られました。これは、全国的な冷害に見舞われた年で、米不足が生じた年です。こういったときには、米価は上昇します。ウについて、コメの生産量は、昭和30年代後半まで上昇していました。そこから下降傾向を示しています。バブル景気のころというのは、1986年(昭和の終わりから平成のはじめ)からの5年間ほどをさしますので、時代がずれています。オについては、コメの作付面積も生産量も、そして消費量もすべて下降傾向です。カは、正確な数値でいえば、現在の一人当たりのコメの消費量は50kgほどです。ピーク時が110kgほどでしたから、問題文後半の最も多かった時期から半減という部分は正しいといえます。イメージをつけるために大まかな計算をしてみたらいかがでしょう。50kgということは、月平均で4.2kgほど。一食が150gほどとした場合、28日分ということになります。1日3食のうち、麺類やパンを食べる頻度を考えると、このくらいという見当はつくのではないでしょうか。以上から、残ったアとエが内容の正しい選択肢と考えられます。
2.
ブランド米の産地に関する問題です。
近年、中学入試においてコメの産地を問う問題が増加傾向にあります。ざっと挙げてみますと、ゆめぴりか・きらら397(以上北海道)、だて正夢・ひとめぼれ・ササニシキ(以上宮城県)、あきたこまち(秋田県)、つや姫・はえぬき・どまんなか(以上山形県)、一番星(茨城県)、ふさおとめ(千葉県)、といったあたりが、コシヒカリ以外で中学入試において出題された実績のあるブランド米です。
3.
小麦の輸入相手国は、①アメリカ合衆国(54.8%)、②カナダ(28.9%)、③オーストラリア(16.2%)でそのほとんどを占めています。その他の輸入品につき上位3位までの国とその割合は試験対策としておさえておきたいことがらです。
4.
小麦の用途に関する問題です。
うどん、パスタ、そうめん、ナンは小麦を原料とした食品です。タピオカは、キャッサバを原料としています。キャッサバとは、南方を主産地とするイモ類の一つです。また、「もち米」という原料が存在するように、もちの原料はコメです。
5.
バイオエタノールは、さとうきびやとうもろこし、またこれらの皮や茎などや木材を硫酸、酵母の液体に漬け込み発酵させたものを蒸留して採れた液体です。アルコールが主成分のため燃焼でき、自動車などの内燃機関の燃料として活用できることに期待が寄せられています。しかし、いいことばかりではありません。とくにとうもろこしは需要が一気に上昇し、生産者は生産拡大をおこなおうと農地拡大のために広大な森林を伐採したのです。また、作物価格上昇により食料供給が不安定化し、とうもろこしを主食にしている人々や、家畜の飼料として利用していた人たちの生活を直撃しました。地球環境に大きな貢献をしてくれると期待されていたバイオエタノールも、このような問題を抱えています。
6.
日本の多くの地方で生産され、日本米の代表的ブランド、「コシヒカリ」です。正式な名称は「こしひかり」ではなく「コシヒカリ」です。現在は、お米の名前にひらがなを使うかカタカナを使うかのルールは特に取り決めはないのですが、かつて、国の試験機関で生産されたコメにはカタカナで、都道府県の試験機関で生産されたコメにはひらがなで命名するというルールが存在していました。コシヒカリは、ずいぶん古くに品種改良により生産されたコメで、しかも国の機関により生産されたため、正式には「コシヒカリ」と登録されたのです。
7.
世界の食文化に関する問題です。
タコスは、とうもろこしの粉をこねて作ったクレープの皮のような生地に、レタスの千切りやひき肉をトマトといっしょにスパイシーに炒めたもの、トマトの角切りなどをはさんだものです。タコスは、メキシコでよく食べられる料理です。
8.
米、小麦、とうもろこしの地方ごとの収穫量を考える問題です。
合否を分けた一題にて解説いたします。
(地理・歴史・公民融合問題)
外国人の行き来や日本人が外国へ渡航した歴史を地理や公民と関連させて問う問題です。
1.
インバウンド(訪日外国人観光客)がどれくらい伸びているのかについての問題です。
近年、このインバウンドという言葉が流行するほど、外国人観光客の訪日数はうなぎのぼりだったことは受験生であれば時事問題的知識としてよくご存じでしょう。問題は、どのくらい伸びているのか。問題本文にあるように、5年ほど前は1000万人ほどだったのが2018年に3000万人を突破したというニュースは、大々的に報道されました。しかし、2020年の初旬からコロナウィルスが叫ばれるようになり、最も低水準を記録したのが4月の、なんと「2900人」です。単位がおかしいのでは?と疑いたくなるくらいの低水準です。インバウンド頼みの観光業界や飲食業界、バス会社などの倒産が相次いでいる状況です。
2.
日本の主要都市(一部の政令指定都市)の人口に関する問題です。
各地の主要都市(政令指定都市)の人口は、ある程度まで(上位10位プラス東京23区)おさえておいたほうがよろしいかもしれません。本問の270万人は、大阪市の人口とほぼ同じくらいの数字です。
3.
聞いたことはあっても、空欄に埋める形で聞かれると難しく感じられるかもしれません。( え )は、ハワイやアメリカ大陸に渡った移民の子孫を何と呼ぶかというように聞かれているのと同じです。これは、「日系人」です。( お )については、1932年に「建てられた」という言葉にひっかかると難しいかもしれません。年号で確定させるか、その後の記述にある「日本の敗戦で引き揚げた」をヒントに考えるか、のいずれかで考えましょう。1932年に「建国」された「満州国」です。敗戦後、ここを植民していた日本は日本への撤退を余儀なくされます。
4.
看板や交通機関の案内図でみられる外国語に関する問題です。
英語のほかに、「中国語」と「韓国語」です。日本にはこの両国からの外国人が多く暮らしていることから、この二つの言葉が使われています。
5.
歴史的出来事の時代を問う問題です。
まず下線部②ですが、卑弥呼が活躍していた時代です。魏から「親魏倭王」という称号を与えられたのが、238年とされていますから、このころをとって3世紀とします。下線部③法隆寺は、607年に建立されています。したがって、7世紀となります。
6.
戦争についての問題です。
下線部④の直前に「江戸時代のすぐ前」とあり、この戦争において、「日本に多くに人が連れてこられた」と記述されています。江戸時代の前ということは、安土桃山か戦国時代です。また、この時代の戦争をきっかけにして、多くの外国人が日本に連れてこられたということは、豊臣秀吉による朝鮮出兵が考えらえます。朝鮮出兵に際して、多くの陶工と呼ばれる朝鮮の人たちが日本に連れてこられ、現代にも残る有田焼などの焼き物を残しました。
7.
中国王朝名の問題です。
日本の歴史と深くかかわる中国の王朝は、数も多くありませんから覚えておきましょう。本問では、下線部⑤で清とされており、その前に中国を支配していた王朝を問われています。これは、「明」です。
8.
日本町に関する問題です。
日本町は、安土桃山時代から江戸の初期(鎖国が完成するまで)に日本人が多く移り住み、町を形成していたものをいいます。当時は南蛮貿易が盛んでしたから、そのほとんどが東南アジアに形成されていきました。したがって、ルソン(フィリピン)、シャム(タイ)、カンボジアが該当します。
(公民)
コンビニエンスストア(コンビニ)に関する問題です。知識よりも様々なことを推測したり、ふだんからの観察力が試されているといえます。
1.
コンビニでの様々な工夫といえるものを選ぶ問題です。
誤っていると思われる選択肢を検討していきます。イについて、コンビニでは特別な照明を使っていることは事実です。しかし、それはお客様が落ち着いて商品を選べるようにという目的ではなく、虫が集まらないように、一般的な蛍光灯を使わずLED蛍光灯を使っているということです。ウについて、売れ筋の商品はレジ周りにおいて、レジ待ちをしている間にもカゴに入れさせる工夫をしています。防犯カメラは、強盗に遭った際にその証拠となる映像を残すことや、万引きを防止するのが目的です。あまり見えるところに数多く設置されていることを想像すると、皆さんはどう思われますか?一般のお客さんは落ち着かないのではないでしょうか。以上から、残ったアとエが正解と思われます。
2.
コンビニでのレジ入力に関する問題です。
POSシステムといわれる手段を使っている場合、レジで金額を入力(バーコードをスキャンする)まえに、性別や年齢層、一人か二人以上の家族連れかなどをレジに入力する作業がありました。これは、どの商品をどのような人が買っているのかということを、統計としてコンビニの本部が把握するためにおこなっていた作業です。しかし、最近はこの作業が減ってきています。なぜかというと、キャッシュレス化が進み、各コンビニともに自社のキャッシュレス決済アプリやカード(nanaco、waon、ファミペイなど)の利用や、交通系カード(suica、pasmoなど)、Paypayといったアプリの利用が増加したことと関係があります。これらのアプリやカードを利用する際、最初に利用客が自分の情報を入力することが要求されることにより、利用するたびに自動的にその情報が本部に蓄積されるようになったのです。したがって、こたえはエです。
3.
最近のコンビニでは、かならずイートイン(食べる場所)が設置されています。また、スマホの利用者が多いことからその需要を見込んで、スマホの充電ができる機械を設置しているコンビニを見かけることも多くなってきました。なお、本問では「店内に」ということばが前についていることがポイントです。
4.
長いこと24時間営業が当然と思われてきたコンビニの営業時間が短縮される傾向にあります。これは、ある程度の来客が見込める店舗であっても例外ではなくなりつつあります。原因は、店員のなり手がいないことです。通常、コンビニはフランチャイズ方式といって、オーナーとなる人が自己所有あるいは他者所有問わず土地に店舗を建て、ロイヤリティー(本部に支払うお金)を支払ってコンビニのなまえ(セブンイレブンやローソンといったなまえ)やシステムを使わせてもらいながら経営します。そして、店舗を経営する際、店舗スタッフが必要になります。しかし現在、コンビニスタッフの募集が思うように進んでいません。コンビニのオーナーも働きやすさを最大限アピールして募集をかけていますが、なり手がとても少ないのです。オーナーは自分の睡眠時間を削って24時間営業を継続しようとしてきましたが、限界に達してしまいました。そして、本部に24時間営業の廃止を訴えたのです。
(公民) 天皇制に関する問題です。
1.
天皇制に関する記述の空欄補充問題です。
まず( ア )は、「旧憲法の」ですから、『大日本帝国』です。( イ )は、忠君愛国を主旨とするとされ「教育に関する」ですから、『勅語』です。( ウ )は、天皇の地位に関する記述です。国の政治のですから『主権』者となります。( エ )は、統帥したという記述につながる言葉ですから『(陸海)軍』となります。さいごに( オ )ですが、新憲法(現日本国憲法)では、『内閣』の助言と承認に基づき国事行為をおこなうのみで、政治的な権能を有しなくなりました。
2.
天皇の地位に関する問題です。
本文だけをみると抽象的でよくわからないように思えるかもしれません。しかし、問題文では、新憲法(現日本国憲法)の中で天皇の地位をあらわす言葉を聞いていることがわかります。したがって、象徴です。
3.
天皇の国事行為に関する問題です。
国事行為が何をさすかは、憲法条文に列挙されています。この列挙以外の政治的行為はおこなえません。問題では、アとオが国事行為に当たりません。たしかに、天皇・皇后両陛下が外国を訪問することはあります。しかし、この訪問は憲法に定められた国事行為ではなく、友好関係を結ぼうとの国の意図や、外国で何かの儀式がある場合、その表敬訪問として訪れていらっしゃるのです。また、東日本大震災が起きたあと、現在の上皇・上皇后お二人が東北地方を毎週のように訪問されていらしたことはご存知でしょうか。しかし、これも憲法に定められた国事行為として行動されていらしたわけではなく、お二人の国民を慮る(おもんばかる)お気持ちから訪問されていたのです。
合否を分けた一題
一見すると、9地方のうち4つが問われており、しかも米、小麦、とうもろこしの地方別の収穫量の割合まで覚えてないよということですぐにあきらめてしまったり、考えはしたがしぼり切れずに時間切れとなった受験生も少なからずいらっしゃったのではないかと推測いたします。
8.
まず、米と小麦ととうもろこしで特徴があきらかなのはどれでしょう。パッと思いつくのは、小麦➜北海道ではないでしょうか。したがって、際立った数値が見られるアが小麦とまず判断します。つぎに、おしなべて全国的に収穫できるのは、米ですね。そこで、イが米ではないかと判断します。のこったウがとうもろこしでしょう。つぎに、地方を検討します。先に述べたように、アを小麦と判断し、際立っているのが北海道ですから、Aが北海道。そして、地方別でコメの収穫量割合を比較して高いのは東北地方です。したがって、Bが東北。ここで気をつけなくてはいけないのは、新潟がコメの作付が高いと理解していると北陸にいってしまいそうです。しかし、北陸と東北で収穫割合を比較すると、1.5倍~2倍くらいの差が生じています。しっかりと覚えておきましょう。さらに米に注目するとDが全国レベルで比較したときに上位に入りそうな数値です。残っているのが、北陸か四国であり、そのいずれがコメの生産が高いかは一目瞭然です。よって、Dが北陸、Cが四国となります。
慶應普通部入試対策・関連記事一覧
慶應普通部入試対策・同じ教科(社会)の記事
慶應普通部入試対策・同じテーマ(合否を分けた一題)の記事
- 算数の合否を分けた一題(2010年度)
- 国語の合否を分けた一題(2012年度)
- 算数の合否を分けた一題(2016年度)
- 社会の合否を分けた一題(2016年度)
- 国語の合否を分けた一題(2016年度)
- 理科の合否を分けた一題(2016年度)
- 算数の合否を分けた一題(2017年度)
- 国語の合否を分けた一題(2017年度)
- 理科の合否を分けた一題(2017年度)
- 社会の合否を分けた一題(2017年度)
- 算数の合否を分けた一題(2018年度)
- 理科の合否を分けた一題(2018年度)
- 社会の合否を分けた一題(2018年度)
- 国語の合否を分けた一題(2018年度)
- 算数の合否を分けた一題(2019年度)
- 国語の合否を分けた一題(2019年度)
- 算数の合否を分けた一題(2020年度)
- 国語の合否を分けた一題(2020年度)
- 社会の合否を分けた一題(2021年度)
- 理科の合否を分けた一題(2021年度)
- 算数の合否を分けた一題(2021年度)
- 国語の合否を分けた一題(2021年度)