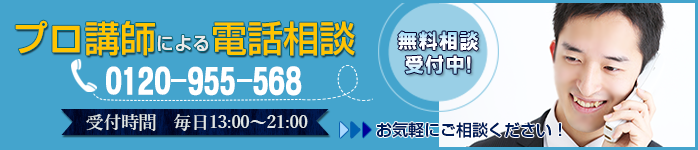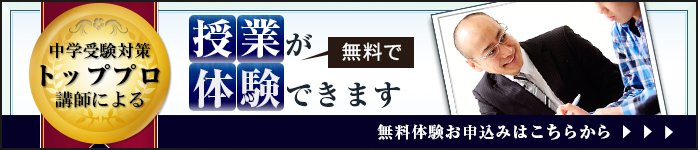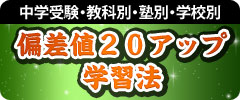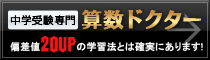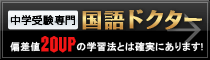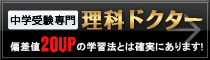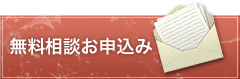算数
フェリス女子中入試対策・算数の出題傾向分析
標準問題+昔ながらのフェリスらしい問題
フェリスの算数は、「受験生であれば一度は解いた経験があるような典型的な標準問題」と「昔ながらのフェリスらしい問題」を組み合わせた入試問題のセットになっています。
後者の問題、つまり、太古の昔から出題されていて、“フェリスのお家芸”とも言うべき問題は、①整数+推理、②近似値と逆算が絡む平面図形、③(逆比を利用して)差に注目、の3タイプです。
「整数+場合の数」というタイプは上位校が好んで出題しますが、フェリスのように①「整数+推理」というタイプを出題する学校はそう多くはありません。また、②のタイプを毎年のように出題する学校はフェリス以外にはないでしょう。
③のように「差に注目」は「和に注目」とともに中学受験算数において必須の着眼点であり、どこの学校を受験するかにかかわらず身につけるべきものです。
時間配分
ここ5年間の受験者平均点の推移は、46点→68点→55点→61点→55点とアップダウンを繰り返していますが、それより以前の受験者平均点は40点台が多かったことを考えれば、随分と解きやすくなった印象があります。
フェリスの入試問題は、難易度順に問題が配置されていないのが特徴です。かつては合否に影響しない高難度の問題が散見され、解けそうな問題と解けそうにない問題がはっきりしていました。捨て問題が明確なぶん、得点を拾うべき問題に時間をかけることができたのです。しかし、最近のように突出した高難度の問題が含まれないケースでは、解けそうな問題が多くなるので、どのような順番で解くのか、時間配分の作戦がより重要性を増してきます。
記述型入試
解答用紙は存在せず、問題用紙の解答スペースに図、式、計算を書き込んでいくスタイル。雙葉中や学習院女子中等科と同様です。また、単位も解答欄に自分で書き込まなければならないので注意が必要です。
[1]の計算問題と一行問題群を除き、[2]以降の大問から(年度によっては[3]から)“求め方”の記述を要求するスタイルは、答えが正しければOKという感覚で取り組んできた生徒にとって、高いハードルとなります。
算数に限ったことではありませんが、書くという作業について及び腰になる生徒、面倒がる生徒は、残念ながらフェリス中には不向きです。それでも、やはりフェリス中を志望したいのであれば、これまでの自分の姿勢を改めなければなりません。鍛えていきましょう。
フェリス女子中入試対策・関連記事一覧
フェリス女子中入試対策・同じ教科(算数)の記事
フェリス女子中入試対策・同じテーマ(出題傾向分析)の記事
同じテーマの記事はいまのところありません。
※ ただ今、当塾の講師陣が一生懸命執筆しております。
執筆がすみ次第、随時公開いたします。
今しばらくお待ちください。