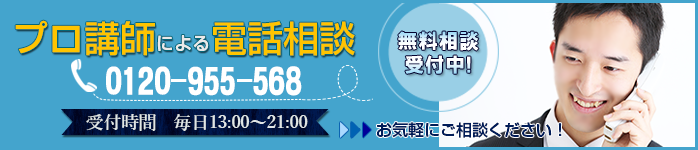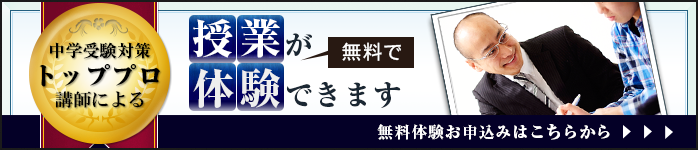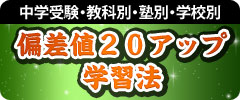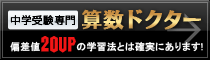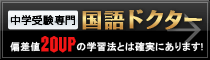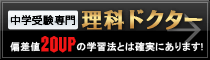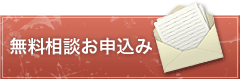国語の合否を分けた一題
慶應普通部入試対策・国語の合否を分けた一題(2021年度)
難易度分類
| 一 | 問一A 問二A 問三A 問四B 問五B 問六B 問七A 問八C 問九B 問十A 問十一A |
|---|---|
| 二 | 問一B 問二A 問三A 問四A 問五A 問六B 問七A 問八B 問九B 問十A 問十一A |
| 三 | A |
A…普通部合格を目指すなら、確実に得点したい問題
B…知識や文脈力、論理的思考力で、得点に大きく差がつく問題
C…国語力がないと歯が立たない問題
総評
今年度は普通部らしさが薄まって、模試に近い形の出題形式が増えました。選択肢問題や抜き出し問題を中心に全体的に易化したので、合格者の平均点はかなり高いものになったはずです。設問の形式を見ていきます。前年同様、大問三題の出題でした。大問一は物語文、大問二は随筆文、大問三は漢字の書き取りです。これまでの普通部の国語には抜き出し問題や条件記述問題が多いと言った特徴がありました。しかし、昨年は7問出題された抜き出し問題が今年は3問しか出題されず、しかも難度がぐっと下がって簡単になっています。また、記述では条件指定がゆるくなり、比較的自由に書けるように変化しました。過去10年間で1問しか出題されていない50字記述が出るなど、記述の字数も増えました。普通部の過去問対策を徹底してきた受験生の中には、長めの自由記述が出てきたことに戸惑った人もいたと思われます。普通部と同じ附属校系の早稲田実業は、抜き出し中心だった独自の問題構成をやめ、数年前から一般的な模試に近い形へとシフトしました。今後の普通部も同様に変化する可能性があります。普通部の受験生は過去問対策を行うと同時に、一般的な記述練習も積み上げる必要がありそうです。
問題別寸評
出典の明記なし
問一
傍線部の比喩を解釈する問題です。「夜」を友人にたとえる擬人法です。「耳しか持たない友人」なので、僕の話を聞いてくれるだけの存在であることが分かります。
問二
傍線部の行動をした「ぼく」の心情理由を答える問題です。傍線部の後にある、「ぼくはシーツをにぎりしめていた…」「目が覚めると、パジャマは汗でじっとりとぬれていた」の部分がヒントになります。
問三
傍線部のように「ぼく」が感じた理由を答える問題です。直前にある「昨日庭から変な音が聞こえたこと、かくさなくてよかったなと気づいた」という部分と、傍線部の後にある「後ろめたい興味」という部分から考えれば答えは明らかです。
問四
傍線部の行動をした「ぼく」の心情を答える問題です。直前の部分では「提出物を忘れたのも、職員室に呼び出されるのも初めてのこと」とあるので、アを選びたくなります。しかし、このあと「ぼく」は大橋先生の言葉から考えたことを話題にしているので、「大橋先生のほめ言葉も耳に入らないほど」という部分が言いすぎとなります。「はあ、とあいまいな返事」をしたのは、ほめ言葉が耳に入った上で、ほめられたことが嬉しいことかどうか分からなかったからです。
問五
傍線部のように「ぼく」が思った理由を答える問題です。本文中には「ぼく」の心情は明示されていませんが、設問にヒントがあります。問十の設問の文章にある「『ぼく』が田島かなえによく思われたいと考えている」という部分から考えましょう。
問六
傍線部のしぐさをした「ぼく」の心情を答える問題です。設問に「『ぼく』がこのようなしぐさをするのはこの文章の中で二回目です」とあります。「ぼく」は一回目にどんな場面で「歯ぐきをそっと舌でなぞった」のかを探しましょう。傍線3の後にあります。両方の場面に共通する心情を答えましょう。
問七
傍線部にある、主人公ではない登場人物の行動の理由を選ぶ問題です。視点人物でない登場人物の心情は地の文では明らかにされないので、その人物の発言や行動、性格から類推していくことになります。田島かなえの人物像にあてはまらないものを除いていきましょう。「学年のあちこちに友達がいる彼女はいつも、教室を仕切る壁さえ見えないとでも言うように、色んなクラスに遊びに行く」ことから彼女の明るく自由な性格が読みとれます。
問八
傍線部の比喩表現を具体化して記述する問題です。本文のどこにも「ぼく」が自身のこれまでの生き方を振り返るシーンはありません。本文にある具体的なエピソードや「ぼく」の行動から、「ぼく」の性格とこれまでの生き方を類推するしかない難問です。大橋先生からほめられたことや授業参観の忘れ物がめずらしいと言われたことから、「ぼく」はいわゆる良い子で真面目だということが分かります。「ぼく」はそんな自分や現状に対して不安や不満を持っていることが傍線部9の段落から分かりますので、良い子であることのマイナス面を、問七の田島かなえと対比させて考えましょう
問九
傍線部の比喩表現で表される「ぼく」の心情を答える問題です。比喩表現自体を解釈するのではなく、「ぼく」が何について考えているのかを類推しましょう。直前の傍線部8に「自分の立っている場所がとても頼りないもののように感じられた」とありますので、昨夜の音のような具体的な事件について考えているわけではないことが分かります。「自分の立っている場所」とは、問八の設問に書いてある通り、「ぼく」のこれまでの生き方です。これまでの自分に不安や不満を持っているのです。
問十
傍線部の「ぼく」の心情が間接的に表れている表現を抜き出す問題です。問十のこの設問から、「ぼく」が田島かなえに好意を持っていることが分かります。田島かなえが出てきて「ぼく」と会話をしている段落に、自分を大人っぽく見せたいという「ぼく」の思いが表れている部分があります。
問十一
傍線部が何を象徴しているのかを選ぶ問題です。問八、問九の設問から、これまでの自分に対する「ぼく」の不安や不満が分かります。そういう現状を変えてほしい、変えたいという選択肢を選びましょう、
「朝日新聞 二〇二〇年九月六日 福島申二氏の文章」より
問一
合否を分けた一題で解説します。
問二
傍線部を言い換える問題です。シベリアという土地で6万人の日本人が死んだことがこの文章の前半のテーマです。シベリアという言葉の言い換えを探すだけでなく、「シベリアで死ぬ」という表現のセットを探してみましょう。「果てる」とは「死ぬ」と同じ意味です。
問三
傍線部にある慣用句の意味を答える問題です。選択肢の文章を傍線部3に当てはめて読み上げてみれば容易に解けるでしょう。
問四
空欄にあてはまる慣用句を選ぶ問題です。「膨大な資料を手作業で突き合わせ」「11年かけて分かる限りのことを調べ上げた」にふさわしい、精魂込めたという意味のものを選びましょう。
問五
空欄にあてはまる表現形式を選ぶ問題です。本文に「歌人」とあるので簡単です。
問六
傍線部を詳しく言い換えた表現を選ぶ問題です。問七とあわせて解説します。
問七
空欄にあてはまる言葉を選ぶ問題です。「良いニュース」というのは、「発症者二桁に減り」ということです。「Cにとって良いニュース」であるので、発症者が二桁になったということが誰にとって良いニュースなのかを考えます。そうすればCの正解はすぐに分かります。また「Dの発症者にとっては深刻なこと」とあるので、DはCと逆の意味であることが分かります。よってDは「一部」か「個々」となりますが、「一部の発症者には深刻」としてしまうと、発症者の中にも深刻な人と深刻でない人がいるという意味になってしまい当てはまりません。よって正解は「個々」となります。そうすると、問六は現在の発症者を指していることが分かります。
問八
傍線部の表現の意味を詳しく説明する問題です。「違和感」というのは「良いニュース」に対する違和感です。「小さな違和感」という「小さな」は、違和感を制限している表現なので、「良いニュース」である理由を選びましょう。
問九
傍線部の理由を記述する問題です。傍線部のすぐ後にある「小さな数も、数として見られるかぎり個々の人間の存在は見失われやすい」という部分から考えましょう。
問十
傍線部のために必要なものを抜き出す問題です。「必要と考えられるもの」なので、抜き出すことばは名詞です。「数の中に人を思」った沼野さん、石原、村山さんの例から探しましょう。
問十一
本文の内容に合っているものを選ぶ問題です。一つ一つ本文と対照すれば正否は明らかです。
問一
漢字の問題です。四字熟語の「晴耕雨読」も含まれています。
問二
漢字の問題です。同音異義語を二組答えるものです。
合否を分けた一題
問一
傍線部のように言える理由を五十字で記述する問題です。普通部の記述は三十字前後のものがよく出題され、書く内容や文末に対しても設問で指定されることが多いです。その中でこの問題は五十字と制限字数が長めで、設問の指示も「このように言えるのはなぜですか」と極めてシンプルです。学校の出題特徴から離れた問題であるので、過去問対策とは無関係な受験生の純粋な記述力によって差がついたと考え、合否を分けた一題として取り上げることにしました。
考え方
「地味ながら意義深い」理由を記述する問題です。このように二種類の表現があったら、それぞれ別々に答えるのが国語記述の基本です。まずは地味な理由を探します。本文の表現をそのまま使うと以下のようになります。
「シベリア抑留の犠牲者のうち、判明している4万6300人の犠牲者の名前を遺族や市民が47時間かけて読み上げ」ていくから。
このままでは字数制限を越えるので、具体的な数字を抽象化してまとめます。
シベリア抑留の膨大な犠牲者の名前を長時間読み上げるから
次に、「意義深い」理由を探します。シンボルスカの詩についての沼野さんの解釈と、追悼イベントについての筆者の解釈を参考にします。
「『大きな数』に塗り込まれることで個々の人間は顔を奪われ、抽象概念に変えられてしまう」「この詩は、そうした全体性にあらがい、個別の存在と価値を守ろうとする」
追悼イベントについての参考箇所
「名前の読み上げは『大きな数』として語られがちな死者を、抽象の海から呼び戻す」
上の2つを合わせて短くまとめ、「意義深い」理由とします。
名前の読み上げは『大きな数』に塗り込まれることで顔を奪われ、抽象概念に変えられた死者を、抽象の海から呼び戻し、個々の人間に顔を与え、個別の存在と価値を守るから
地味な理由と意義深い理由をつなげます。
重複している表現をなくし、過程を省いて字数制限に合わせます。
慶應普通部入試対策・関連記事一覧
慶應普通部入試対策・同じ教科(国語)の記事
慶應普通部入試対策・同じテーマ(合否を分けた一題)の記事
- 算数の合否を分けた一題(2010年度)
- 国語の合否を分けた一題(2012年度)
- 算数の合否を分けた一題(2016年度)
- 社会の合否を分けた一題(2016年度)
- 国語の合否を分けた一題(2016年度)
- 理科の合否を分けた一題(2016年度)
- 算数の合否を分けた一題(2017年度)
- 国語の合否を分けた一題(2017年度)
- 理科の合否を分けた一題(2017年度)
- 社会の合否を分けた一題(2017年度)
- 算数の合否を分けた一題(2018年度)
- 理科の合否を分けた一題(2018年度)
- 社会の合否を分けた一題(2018年度)
- 国語の合否を分けた一題(2018年度)
- 算数の合否を分けた一題(2019年度)
- 国語の合否を分けた一題(2019年度)
- 算数の合否を分けた一題(2020年度)
- 国語の合否を分けた一題(2020年度)
- 社会の合否を分けた一題(2020年度)
- 社会の合否を分けた一題(2021年度)
- 理科の合否を分けた一題(2021年度)
- 算数の合否を分けた一題(2021年度)